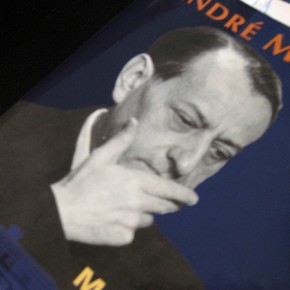
アンドレ・マルロー、文化省発足前夜 1
時間が経過しても、見直す意義のあると思える文章がいくつかある。これは、2002年、アンドレ・マルローの生誕100年を記念した年に、『ふらんす』(白水社出版月刊誌)に掲載した拙文。戦後初めての文化省設立に英知を注いだアンドレ・マルローの資料周辺を翻訳し、掲載用に短く取りまとめたものである。(Tag:アンドレ・マルロー、で記事検索) ------- 現代文化と政治、その関係の始まり <文化大臣、アンドレ・マルロー生誕百年に寄せて>…

Lille Fantastic – リル3000、ファンタスティック
Lille Fantastic! リル市で3ヶ月にわたる巨大文化フェスティバル 10月6日土曜の夜、町を埋め尽くす30万人という群集のなかで花火と張りぼてモンスターたちの行進で始まった、ヨーロッパのメトロポールと呼ばれる町リル市の文化フェスティバル、「リル3000、ファンタスティック2012」が開幕した。800の現代アートを含むさまざまな展覧会を含め、コンサートやパフォーマンス、ダンスやストリート・インスタレーション、コンフェランスやシンポジウムなど豊富なプログラムをかかえて、来年2013年1月13日までフランス、ノール県リル市のいたるところで開催される。 オフィシャル・プログラム、リル3000、ファンタスティック2012 http://www.fantastic2012.com/ プレス: リル3000 ファンタスティック(Metro) リル・ファンタスティック(カルチャーBox)

フランスTVブログ、カルチャーボックス紹介
フランスTV(テレビ)のブログには文化欄Culturebox(カルチャーボックス)が設けられ、現代文化のニュースを膨大な量の情報で網羅している。 Cultureboxは、映画(Cinéma)、展覧会(Expositions)、音楽(Musique)、劇場(Scènes)、傾向(Tendances)、本(Livres)の6項目に別れ、各項が国際的なイベントを含む沢山の情報を提供。…
現代文化と国について 2
“L’Art à tout prix!(どんな代価を払っても、アート!)” フランスは、公が「文化」を語ることが少し前まで一つの日常だったのだが、ここ数年は政治と経済の話ばかりが先行して、文化が語られる機会がまったく僅少になってしまっている。むかしは、国が保護をすることで、荒々しい経済の波から少しでも切り離し、創造されるものが政治的な道具とならないように、文化の論理を真摯に解きほぐす態度が公の側に常に存在していた。国の元首であるミッテランやシラクが、政策の左右にかかわらず、政治のディスクールに必ず文化を基盤におき、「フランス文化の特殊性」「文化の多様性」といったフランスの文化的アイデンティティーを明確にする常套句をあみだし、われわれはそれを毎日のように彼らの口から繰り返して聞いた。フランスの空気は文化ということばで充満されていたと言っても過言ではないと思う。 2007年以来そんなことはついぞなくなり、近年は文化と文明がごちゃ混ぜ。…
アクチュアリティ
冷夏 - バカンスに入ったとたん、フランス全土を冷気が包んだ。あちこち雨、アルプスでは標高2600メーターで雹、続いて降雪。アルプス山岳地帯で転車競技を楽しんでいた約200人が、冷気を超えた寒気に襲われ消防隊に救助された。自転車競技参加者はショートパンツに半袖の軽装。大雨のあと気温が急降下して3度まで下がり、雪に見舞われるなどして、寒さで体が硬直し動けなくなったため。 ブルターニュ、太平洋岸はスペイン国境近くまで平年より7度から5度低い気温に、海水浴をする人はほとんどいない。ドイツやイギリスからの旅行者も、悪天のフランスに飽き飽き。海岸近辺の商売は上がったりだ。冷夏は7月下旬まで続くもよう。 マルチーヌ・オーブリィ、文化予算倍増を提言 - 雨のアヴィニョン・フェスティヴァルを訪れた社会党のマルチーヌ・オーブリィは、5年をかけて文化予算を30%から50%増加することを提言した。フランスは「文化の多様性」に立ち返り、文化を活発化しなければならないとし、現政府、ことにサルコジ大統領の文化離れを批判した。 ちなみにフランスの文化予算は減るどころか増える一方だという。2011年の文化予算は、75億ユーロ。うち、3億7500万ユーロは、歴史建造物へ、6億6300万ユーロが舞台芸術に、4億2000万ユーロが(困窮状態の)報道関係へ費やされている。(フランス2TV) My opinion: マルチーヌ・オーブリィのみならず社会党議員たちのなかには、現代芸術へ思いを寄せ、地方レベルで支援増大を実行している議員が大勢いる。昨年私が参加したルーアン・アンプレッショネ展も、今年のメル現代アート・ビエンナーレも、そうしたかれらの予算増大の賜物の展覧会なのである。シラク以前の革新政府時代は、文化予算といえば現代芸術の「創造にたいする支援(Soutien à la création)」が必ず大きな位置を占めていた。時代が変わったサルコジ政権下のきょう、フランス2TVが引用した文化予算の内訳に、そうした創造のための予算が言及されなかったこと自体がすでにおかしい。その上、4億2000万ユーロが報道関係の救済(Aide à la presse en difficulté)というから、文化のなかでもどういう形態のものに多額な予算が利用されているか、推して知るべしである。サルコジ政治で2007年を境に、めっきり文化の話が減少した。そう、多くの人が感じている。少しのあいだにズレてしまった文化の真意を取り戻し、文化予算も内容をうんぬんすべきときにきているのではないか。(S.H.)
現代文化と国について
数日前にこのブログで、フランスは外国人に永住権も与えないし、法的に職業規制があったりで思った職業にも就けない、という話をした。 「私たちは芸術家でよかったわね。芸術家にはだれだって自由になれるのだから」と同じ建物に住むスエーデン人が言ったことがあった。フランスの外国人は自由に職業を選ぶことができないという硬派のフランス社会についてはなしをしている最中に飛び出した意見だったが、このときの私はうーんとうなったばかりでうまい返事は出てこなかった。国から何の制限もない芸術家職は、そんなフランス社会の厳しいプロテクショニズムとは関係がない、とこのスエーデン人は言いたかったらしい。しかし、本当にそうだろうか。周りの人々が汲々として決められた制限のなかで生きているのに、そうした色に染められた社会の見識から免れて芸術家だけが自由を享受できる、というのはむしのいいはなしではないだろうか。 20年近く前フランスは、現代文化において「政府メセナ」のモデルとして日本でも盛んに紹介された。私企業のメセナが多く立ち上がったアメリカや日本と違い、フランスは政府が現代文化を援助する大きな体制を作り上げたからだ。資本主義の米日が「民」ならば、社会主義よりのフランスは「官」、として国のあり方を対立させてみてもいいかもしれない。フランスの企業はその大多数が国が株主で「公社」であったから、もともと私企業のメセナが育つ土壌も当時は僅少だった。そうした国の経済のありかた同様、現代文化もフランスは政府が指揮を取って政治のうえで采配しようとし、1981年、フランス文化省を復活させた。 この文化省に、現代アートを支援する「造形芸術庁」が発足して現代芸術のメセナ的な仕事を始めることになるのである。その仕事は実に緊密で、まずは「現代アート」の定義からスタートする。国の言う現代アートとは、狭義の流行のアートのことを指すのではなく、現代生きて仕事をしている作家が生み出すアートすべてを指す。したがって、すべての生きて仕事をしているアーティストとそのアートを対象にしている。生きているかぎり芸術家は、他の職業者同様、税金を払わなければならず社会保障も受けなければならない。そうした社会の一員としての義務が果たせるように国がメセナ的役割をもってサポートし、実利的な仕事を創造してアーティストにリンクをする役割を自分に課した。(公団住宅の枠内で芸術家用アトリエ建設、作品買い上げと作品公庫の設置、芸術活動への援助金制度、カタログ援助、展覧会援助、コマーシャルギャラリーとは質の異なるアートの発表を目的とした展覧会施設開設と相互リンク、公共建造物に作品を入れる法律〈1%〉、情報センターなどの芸術活動に必要なネットワークと施設を設ける、等々。) 国の現代芸術政策は、なかば芸術家の生活に結びついた福祉的な性質を大きく含みつつ、芸術育成をめざした組織的な構造が徐々にまた全国レベルで作り上げられていったのだ。 さて、現代芸術のリーダーがフランスの「国」であることは、何を意味するだろうか。現代から将来に向けて創られる現代文化も、ここでは政治の一環となっているわけだから、文化再興の理論の底流には、フランスのプロテクショニズムが大いに働いている。 1960年に初めてできた文化省は、初の文化大臣アンドレ・マルローの省内スタッフによってその真意が明らかにされている。「将来、世界が望むようにフランスの精神的尊厳を回復し、文化の(世界における)指導的立場をとりもどすことを念頭に、(戦後退廃しておざなりにされ、すっかり他の国に追い越されてしまった)フランス文化を建て直す」ことを大目的とすると。そうして1981年の文化省の再興は、マルローの意思をそっくり引き継ぐ作業の実現から始まっていることを指摘しなくてはならないだろう。 外から来た文化人たちは私を含め、フランスから跳ね返されるような勢いをしばしば感ぜずにはいられなかったのは、それだけ当時、この国の現代文化政策がエネルギーを持っていたことを意味するのだと思う。このフランスの勢いのおかげで、文化という大きなテーマについて、フランスの長い間の論議を認識する機会を何度も得ることができた。また、自分がいるフランスからフランスの思想をもってはじき出されることで、自分はそれではいったいどの文化に向かって作家活動をしているのだろうか、という疑問につきまとわれるようになってしまっている。 フランスに来なければ、この国が長いあいだ熟成してきた「文化」への論理的アプローチのなかに浸って、文化とは何かという大命題に接する機会はおそらくそうそう無かっただろうから、フランスには大いに感謝をしているが、一方で、この国で活動を始めてすでに27年たったいまも、自分がどの文化に向かって制作を続けているのかという疑問は疑問のまま、将来もきっと解決することはないだろうと思っている。(S.H.)
もう一度現代文化、サルコジの文化嫌い
いつの間にかサルコジ攻撃をするほうに回って、アクチュアリティなどもサルコジ批判に関連するニュースを多く取り上げるようになった。思い出すのは、ニコラ・サルコジが大統領に選出された2007年の初夏、フランスの全国紙『リベラシオン』の第一面は、ほぼ毎日がサルコジ批判だったことだ。『リベラシオン』はどちらかというと革新系の新聞だが一般庶民的な新聞でもあり、たとえばサルコジが「ナショナル・アイデンティティ」を提起しはじめ、世間が大騒ぎをし始めたころ、新聞の第一面に北アフリカ系の顔をした「フランス人」が、レントゲンの機械の向こうに立ち、こちらから医者が虫眼鏡で映し出されている白黒のレントゲン写真を「骨の髄まで」フランス人かどうか検査している風刺漫画が描かれたりしていて面白がって読んでいたが、記事の内容はというといかにも深刻で、ユダヤ系フランス人が身分証明の更新のときに、役所で「宗教証明」なるものを提出するように命令されたとか、十年以上フランスで出稼ぎをしてお金をためた外国人が家族を故郷から呼び寄せようとしたところ、法律改定でそれが不可能になり、家族は別れ別れのまま一緒に住めないとかいった、フランス人や外国人の扱いに関する細則がじわじわと締め付けるように改定されていくというものだった。…

 オフィシャル・サイト shigeko-hirakawa.com
オフィシャル・サイト shigeko-hirakawa.com 市販カタログ "Regard d'artiste"
市販カタログ "Regard d'artiste" ウォーター・フットプリント・プロジェクト・ビデオ
ウォーター・フットプリント・プロジェクト・ビデオ