時間が経過しても、見直す意義のあると思える文章がいくつかある。これは、2002年、アンドレ・マルローの生誕100年を記念した年に、『ふらんす』(白水社出版月刊誌)に掲載した拙文。戦後初めての文化省設立に英知を注いだアンドレ・マルローの資料周辺を翻訳し、掲載用に短く取りまとめたものである。(Tag:アンドレ・マルロー、で記事検索)
-------
現代文化と政治、その関係の始まり
<文化大臣、アンドレ・マルロー生誕百年に寄せて>…
文化省発足前夜、1956年政府覚書
1956年のフランスにおける芸術全般の嘆き。以下の文章は、共和国政府覚書に認められたものである。
「あるユーゴスラビア人は、ラジオで、<私はフランスが好きだ。何故ならば私はフランスの芸術が好きだからだ>と述べた。この言葉は簡略にして明快に外国のフランスに対する気持ちを表している。ところが、ベルギー人、スペイン人、オランダ人を交えた討議でベルギー人は、<しかしフランスの芸術が隆盛であったと言えるのは今世紀初頭までのことで、現在フランスはそれを維持する状態に入り、実情他の国に抜かれてしまっている>と述べ、外国の実例を列挙した。満座はベルギー人に賛同し、フランスは色を失った。さきのユーゴスラビア人は、フランスの過去の芸術文学の偉大な業績に夢を馳せたのに対し、ベルギー人はフランスの現代に言及したのである。「実際、帝政失墜後のフランスは、何も創造しおおせてはいないではないか」、と。
政府覚書は、続けて個々の芸術を眺望する。「確かに、第三共和国政府は、経済、社会問題、植民地問題に多大なエネルギーを費やしたが、芸術にはなんら政策を持たなかった。イーゼルにたてて描くような種類の画家がいくらか政府のプロジェクトに参画できたとはいえ、壮大な記念碑になるような絵画などは創造されず、制作に一層の費用がかかる彫刻などは微塵も省みられなかった。セザンヌ、スーラ、ボナール、レジェ、デュフィー、ピカソ、ルオー、マイヨールといったアーティストたちを政府はまったく無視してしまっていた」。政府が無視した報いを悔いるときがやってくる。「新しいものを創造しなかったばかりではなく、美術館の保存がきちんとしていたかというと、そうではない。大量の作品がアメリカに流出してしまった。先年、『ダヴィッドからトゥールーズ・ロートレックまで』というアメリカ企画の展覧会が開かれた折、フランスは心底苦汁を嘗めることになった。自国が生んだダヴィッド、ドラクロワ、プリュードン、ジェリコー、クールベ、ピサロ、モネ、ルノワール、スーラ、ゴッホ、トゥールーズ・ロートレック、セザンヌなどの作品を、アメリカが貸してくれたことに、フランスは開会式上で謝辞を述べなければならなかったのである」。
音楽については作曲家のアルチュール・オネゲールの言を引いている。「有名な交響曲というのはすでに大衆の誰もが知っていて、書庫の中の一つの蔵書のように共通の知識になってしまっている。いつでもどこでも演奏されているので、いまさらの練習も必要としない。ところが新作は、多くの練習を必要とする。オーケストラも曲の理解に時間がかかる。知られたクラシックなら客も入るが、新曲では客が呼べない。だいたいハイドンやモーツアルトの時代には、大衆が彼らの新作を要求したものなのに、今日はそうではない。今の大衆は新曲を聞きに来るのではなくて、よく知られた曲を聞きに来るのである」。
新作を求めない大衆は、「音楽への好奇心が欠如している」のだ。「音楽を啓蒙しようにも、公共の大きなコンサートホールがない。私営に任せきりである。コンサートをすること自体、音楽家の負担が大きすぎて音楽家に一銭も残らない。勢い、客の入る曲を選ばざるをえない」。覚書は続けて、「大衆の音楽への好奇心欠如は、音楽教育の欠如であり、その責任は国にある。創作からその設備に目を移せば、音楽学校とてコンサートホールを持たない。我が国では劇場やサーカスで音楽家が演奏をしているような始末ではないか! 」。
これから芽生える芸術への援助政策が、隣国イギリスのアート・カウンシルに先行されているばかりか、美術館組織、音楽、建築、考古学、歴史建造物など、ありとあらゆる方面の慨嘆の現実を列挙して包括し、フランス文化の憂うるべき状況を記録に認めた。1956年12月の『芸術省のために』と題されたこの政府覚書は、現状を大本に、「世界が望むようにフランスの精神的尊厳を回復し、文化の指導的立場を取り戻す」ことを究極の大目的に掲げ、これを国家事業に持ち込むための助走として書かれたのであった。
3 年後、アンドレ・マルローがド・ゴール大統領に指名されて、国民の期待通り、戦後の初代文化大臣に任官する。論議の沸騰点で<文化省>が成立した。国民の無関心、長年の国の無策による頽廃と損失、財政ゼロ。すべての問題を丸抱えにした省成立であった。
生きた文化、死んだ教育
文学者が文化大臣になった。表現力の豊かなマルローの存在がしたたかなら、省のチームを構成するブレインも押し出しが強い。もともとは教育省が文化も包容してまさに日本の文部省と文化庁の関係のようであったのを、教育から切り離すことで文化省はできた。
文化が教育から独立しなければならなかった理由について、新設省が渾身の檄を飛ばす。
「現状の文化とは、引き継がれていくものが移り変わっていくことなのだ。死んだもの(固定概念)の秩序を知ることにばかりとらわれていては文化を理解することはできない。過去の知識に捕らわれ、生きているものに目をつぶり、新しい文化を拒絶する教養人もいる。ラファエロを信じるか故にセザンヌを拒み、セザンヌを擁護するが故に表現主義の色だけの絵を拒んだように。過去は現在を否定する。教育は過去の知識以上の何者でもないのである」。
固定してしまった知識を「死んだもの」と言明するところがすさまじい。「科学的教育が現在を知らないわけはないが、現在を隔離するゆえんは、科学的知識の方法が現在を取り扱うことができないことにある。科学は全体的教育を目指していて、体験的参入を許さない。科学は死が必要なのだ。なんとなれば、死からにのみ表象の意味と総括を与える定義を把握できるからである。死のみが、一般概念へ帰結される関係を把握し、演繹的に広がってゆけるのである。この意味で、現代文化や現代の創造行為などを知ることは不可能なのである」。要するに、教養が必須とするものは定義と体系でありそれらが動かないでいてくれるための「死」なのである。
一方で、現代文化を「生きているもの」と言い、体験的参入のできるものと言う。生と死のように相いれないものを一つの省にまとめておくのは不都合でしかない。体験的に係わって初めて理解されていく文化には、死を前提とする一般教育とは別個の、芸術教育*が必要なのである。
新設省がメセナになる
教育省から独立する理由はこればかりではなかった。「常に教育は問題をかかえているから教育省の予算はこれらの重要な問題の方へ流れがちだ。文化は後回しになるばかりである」。
省を成立させるということはまた、教育省の予算配列の順序待ちからのがれ、独立した予算を持つことにあった。独立後の運営に当たり、すでに1956年の覚書中では、国民の関心を高揚すること、芸術家たちの援助を惜しまず、また、過去の遺産を保存する、というおおよそ3つの大目的を設定してる。
「新省が、芸術振興のメセナとなりうるか」という疑問点についての論及は甚だしい。「現今(新省設立前の)政府は、好んで、個人のメセナに責任をおしつけ職務転嫁をしてきた。パリのオペラ座も国立ダンスアカデミーも、その財政難を個人のメセナが自分の財産を放出してまで支えてきたことは周知の事実である。それら篤志家たちが亡くなると同時に全てがたちゆかなくなった。個人が亡くなれば篤実も消滅する」。
それでは、政府は保存に力を入れていたのかというとそうでもない。「美術館がその収蔵品を充実させる機会があったのに、政府は手を貸さなかった。カーンワイラー・コレクションやカイユボット・コレクションなどの有数の寄贈がありながら、当時の内閣がマネもピカソも嫌いだったという理由で卑下されてしまったのである」。歴史の悔悟は尽きることがない。
国のメセナと略称される現在のフランスの文化政策は、大臣マルローと新設省のチームがこれら当時の実情を下敷きに描きだした文化政策の構想を土台にして立ち続けている。マルローの文化省がどのような具体的策を打ち出したのか、本題に入る前にこの稿も終わりになった。長い年月と政治の変転を越えて膨大な事実が堆積している。それをちょっとづつ齧るようなかたちでしかないが、また紙幅があれば続きを試みてみよう。
(了、ひらかわ しげこ)
-------
現代文化と政治、その関係の始まり、<文化大臣、アンドレ・マルロー生誕百年に寄せて>: 白水社『ふらんす』、2002年2月号、平川滋子連載「コンテンポラリー・アート」に掲載。当該ブログ用に本日加筆。
*芸術教育:フランスの芸術教育、美術学校運営はフランス文化省が行っている。
My opinion: 1996年、シラク政権下の文化大臣フィリップ・ドゥスト=ブラズィがアンドレ・マルローの文化省設立時における資料を集めて文化省がこれを公表した。現実と理想の狭間にあるアンドレ・マルローのアプローチの集積である。『ふらんす』に掲載したこの文章の最後に、「また紙幅があれば続きを試みてみよう」と書いておきながら、肝心の本題「新省はメセナになりうるか」は結局同じ雑誌には書けなかった。14年も経ってしまっているが、やりかけの仕事をまた引き継いで、このブログにアップすることを考えている。(S.H.)

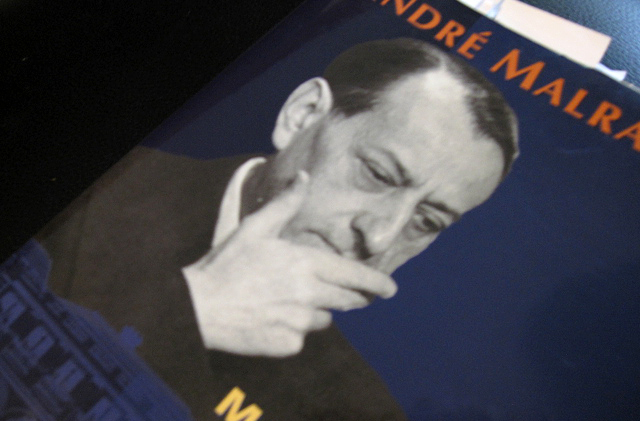
 オフィシャル・サイト shigeko-hirakawa.com
オフィシャル・サイト shigeko-hirakawa.com 市販カタログ "Regard d'artiste"
市販カタログ "Regard d'artiste" ウォーター・フットプリント・プロジェクト・ビデオ
ウォーター・フットプリント・プロジェクト・ビデオ