
6月21日、フランス全国音楽祭
フランス全国各地で行われる音楽祭 路上で、バーで、クラシックからポップス、民謡やその他多彩な音楽が町中に溢れる一年に一度のお祭り。1982年に始まった音楽の祝日はフランス文化省のバックアップで。 2011年には音楽祭は国際化し、30年にして5大陸の110カ国、340以上の都市が参加。
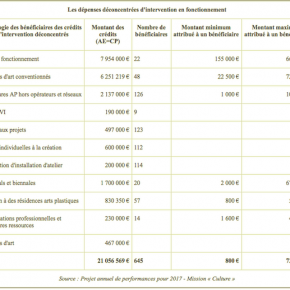
レジデンス・ミッションに思う
流用されるアーティスト・イン・レジデンス、代用教員化していくアーティスト アーティスト・イン・レジデンスがプロジェクトを構想したり実現したりするアーティストとそのクリエートのためのツールだったのは、過去のことになったのだろうか。現代文化政策の中にすべりこんできた聞きなれない「レジデンス・ミッション」という言葉が、ここ数年でフランス中に定着してしまったのは、昨今の大勢とはいえ不本意な話である。

ヨーロッパ美術館の夜
ヨーロッパの3000以上の美術館が無料開館する「ヨーロッパ美術館の夜」は、2017年5月20日土曜の夜中まで。特別イヴェントが行われる。 各地のプログラムはこちら:http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/nuit-des-musees-2017-le-programme-pres-de-chez-vous-18-05-2017-6960780.php
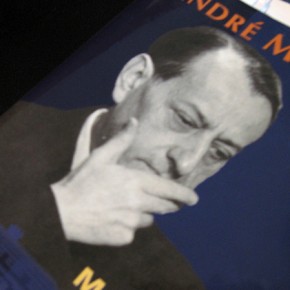
アンドレ・マルロー 2
1952年、美術批評家でありジャーナリストのフランク・エルガーがアンドレ・マルローにインタビューをし、マルローの口から早くも国の文化指導の立場にあるべき人間の資質を浮き彫りにした貴重な文面。
学長の突然の更迭、パリ国立高等美術学校
パリ国立高等美術学校、いわゆる「ボザール」の学長ニコラ・ブリオー(Nicolas Bourriaud)が7月3日、フランス文化大臣フラー・ペルラン(Fleur Pellerin)と芸術創造総事務局長のミシェル・オリエ(DGCA Michel Orier)との35分の会合の後、突然学長職から退くよう言い渡されたことで、美術関係者や学生の間から大きな不満の声が上がっている。 ニコラ・ブリオーは2000年のパレ・ド・トーキョー開館に尽力したディレクターの一人で美術批評家としてもよく知られ、2011年からパリのエコール・デ・ボザールの学長に就任し「時代の要求にあわせるべく」学内改革を進め、昨年任期更新を終えたばかりで、今回の更迭はいわれなき青天の霹靂。学生たちは「馬鹿扱いされた思い」と形容。現代アート作家らは結束して文化大臣に更迭取り下げ要求の手紙を宛てるなどし、美術関係者のあいだから署名運動が広がっている。
「モニュメンタ」がフランスの経済危機で縮小か?
現代アートのアニュアル・大イベント、「モニュメンタ」がフランスの経済危機で縮小か? (フランスTVブログ、カルチャーボックスから) フランスの現代アートにおける国際的な地位を強化し、できるだけ大多数の人々にさらなる現代アートへの門戸を開くために、フランス文化省の肝いりで、パリ、グランパレを舞台に世界に名だたるアーティストを招聘して個展を開催し始めてから、今年で5年目。2007年アンゼルム・キーファー、2008年リチャード・セラ、2010年クリスチャン・ボルタンスキー、2011年アニッシュ・カプーア、そして今年2012年はダニエル・ビュレンを迎えて行われた「モニュメンタ」。ダニエル・ビュレンの展覧会は入場者数26万人を数え大成功を博した。しかしこのモニュメンタ、どうやら政府の緊縮財政のあおりを食らって縮小の危機に瀕しているもようだ。…

Palais de Tokyo 現代アートセンター
Palais de Tokyo パレ・ド・トーキョー 現代アートセンター - 2001年フランスで初めて私企業の支援を主体とする現代アートセンターとして開館。現在はフランス文化省の支援を50%受けて運営し、文化省提携現代アートセンターとして全国の現代アートセンターと名を連ねている。初代名誉館長はピエール・レスタニ(2003年死去)、初代ディレクターは、ニコラ・ブリオとジェローム・サンス。 現代作家の展覧会を開催。 artist in residence : アーティスト・イン・レジデンスの応募を受け付けている (毎年12月15日受付締め切り)。 また、現在パレ・ド・トーキョーは地下の拡張工事を行っており、2012年には9000平米が開館しそのうち5500平米が展示室として利用されることが決定している。 Palais de Tokyo site de création contemporaine 13, avenue du Président Wilson, PARIS Métro Iéna Bus 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92 RER C, Pont de l’Alma Informations +33 1 47 23 54 01
もう一度現代文化、サルコジの文化嫌い
いつの間にかサルコジ攻撃をするほうに回って、アクチュアリティなどもサルコジ批判に関連するニュースを多く取り上げるようになった。思い出すのは、ニコラ・サルコジが大統領に選出された2007年の初夏、フランスの全国紙『リベラシオン』の第一面は、ほぼ毎日がサルコジ批判だったことだ。『リベラシオン』はどちらかというと革新系の新聞だが一般庶民的な新聞でもあり、たとえばサルコジが「ナショナル・アイデンティティ」を提起しはじめ、世間が大騒ぎをし始めたころ、新聞の第一面に北アフリカ系の顔をした「フランス人」が、レントゲンの機械の向こうに立ち、こちらから医者が虫眼鏡で映し出されている白黒のレントゲン写真を「骨の髄まで」フランス人かどうか検査している風刺漫画が描かれたりしていて面白がって読んでいたが、記事の内容はというといかにも深刻で、ユダヤ系フランス人が身分証明の更新のときに、役所で「宗教証明」なるものを提出するように命令されたとか、十年以上フランスで出稼ぎをしてお金をためた外国人が家族を故郷から呼び寄せようとしたところ、法律改定でそれが不可能になり、家族は別れ別れのまま一緒に住めないとかいった、フランス人や外国人の扱いに関する細則がじわじわと締め付けるように改定されていくというものだった。…
時代を変える鍵
九州派の桜井孝美がパフォーマンスで出版した『パラダイスへの道』のおかげで、出版に寄せて1992年および、1993年辺りに書いた拙文が残っている。時間が経っているせいか、1986年のはなしすっかり忘れたようにまったく関係のない当時の時事問題を書いている。 1992年は地方選挙で社会党が大敗。社会党離れはそのまま1993年春の総選挙になだれこんで社会党は5分の一議席しか取れず、内閣解散。再び革新社会党のミッテランを大統領に、エドワール・バラデュール首相を筆頭に内閣はすべて保守系閣僚で組織される保革共存政府が成立した。第一回保革共存政府は、1986年から1988年まで。第二回目の共存政府はこの1993年3月29日から1995年5月まで、つまりつぎの大統領選挙まで続いている。 1993年は、フランスの経済危機で、ル・モンドが「オイル・ショック以来の深刻さ」と書きたて、失業率は3百十万人で11%に届き、中小企業はおろか大企業まで倒産縮小が相次ぎ、エイズ汚染血液の公判が始まり、またインサイダー問題やらなにやらで問題続きの年でもあった。美術界はと見ると、やはり画商の大手が倒産している。すでに1991年の湾岸戦争の影響でマーケットが大幅に萎縮し、ロバート・ロンゴの個展を大々的に行ったギャラリー・アントワンヌ・カンドーが活動停止し、ボードワン・ルボンが倒産請願を提出した。そのころ、私も3つほどの画廊と仕事をしていたが、この年これらの画廊は潰れるか、生き残るために転職をしてしまっている。この恐慌で、あっという間に世の中ががらりと変化してしまった。そんな年だった。 93年下半期、ミッテランが危機を乗り切るために経済対策を発表した。国営企業の24社を民営に移管するよう通達したのだ。この24社は、ルノー公社、エール・フランス、アエロ・スパーシャルなどフランスを代表する大手企業が大半を占め、国の経済を牛耳る元来の社会主義的な体制を解き、いよいよキャピタリズムへ、大きく国の方針が転換することになった。 さて、そのうらがわをよく見てみると、保守派首相のバラデュールは、第一回目の保革共存政府の折に、経済、財務、そして民営化をかねた省の大臣に就いている。むかしから保守派は国営企業の民営化を選挙のたびに公約の一番目においており、1986年も政権を執るとこれを真っ先に遂行した。 93年の経済危機は、そうした保守が大規模な民営化を促進する格好の口実となったのではないか、と漠然と考えたりしている。現実はしかしながら、国営企業は昔ながらのがんじがらめの体制も手伝って一朝一夕に民営化はかなわない。株を少しずつ売りさばいて民間の株主を増やしていくにはかなりの年月がかかっている。 93年の保守内閣の文相はジャック・トゥーボンで、さいわい現代美術に造詣が深かった。大臣になる前はパリの13区の区長でもあり、区内にモニュメントを建てたり集めたりし、またFIAC(パリの現代アートフェア)を訪れる姿を見かけたりすることもあった。 彼の下で文化省はあまり変形されずそのまま推進されたのではないかと想像しているが、問題はほかにあった。文相トゥーボンは、フランス語の乱れを嘆き、それを英語のせいにして「一切、英語を使わない」よう通達してしまったのだ。通達、というのは一種の規則のようなもので、守らなければならない。TVやラジオなどの報道関係は特にフランス語だけで話をするように強制されてしまったかたちで、英語の不得意なフランス人はますます世界から切り離されてしまった。フランスの一般がこの通達にあきれて文化大臣を酷評したのはいうまでもない。 さて、フランス語に関して、後年、特に公文書について国会で意見を述べたエリザベット・ギグの話をここに引いておきたい。 エリザベット・ギグは1997年から2002年、保守シラク大統領の下の革新派ジョスパン内閣で法務大臣に就いた社会党のインテリである。ジョスパン内閣が女性議員を増やし男性議員と同数にするための政策をすすめていた時期だったこともあるが、エリザベット・ギグがある日、国会演説のなかでこう述べた。「公文書は今まですべて男性によって書かれたもので、表現も内容も男性のものということができる。これからは女性が公文書を書く機会を増やし、これまでの公文書も女性の観点で検討されてしかるべきだ」。 この日、この演説を聴いて私は目から鱗が落ちる思いがした。こうした観点がおそらく時代を変える大きな鍵になるにちがいない。(S.H.)

 オフィシャル・サイト shigeko-hirakawa.com
オフィシャル・サイト shigeko-hirakawa.com 市販カタログ "Regard d'artiste"
市販カタログ "Regard d'artiste" ウォーター・フットプリント・プロジェクト・ビデオ
ウォーター・フットプリント・プロジェクト・ビデオ